はじめに
生成AI(Generative AI)は、文章や画像、音楽、コード、動画など、さまざまなコンテンツを自動で作り出せる技術です。最近ではニュースやSNSでもよく取り上げられ、私たちの生活にも身近な存在になってきました。本記事では、生成AIの基本から代表的なツール、使い方のコツ、日本での活用事例、注意点までをわかりやすく紹介します。
1.高校生にもやさしい生成AIの基本と進化
生成AIは、人間のように「新しいものを生み出す」ことができるAIです。これまでのAIは「分析して予測する」ことが得意でしたが、生成AIは「ゼロから創る」ことが得意です。
たとえば:
-
読書感想文の下書きをAIに考えてもらう
-
美術の課題に使う背景画像をAIで作る
-
音楽の授業でBGMを作ってみる

こうした使い方がどんどん広がっています。今では文章の作成や画像生成、音楽制作、プログラミング、動画編集など多岐にわたる分野で活用されており、まさに「デジタルな相棒」といえる存在です。
2.どんなサイトがあるの?生成AIの種類と有名なツール
生成AIには用途ごとに多くのツールがあります。ここではジャンル別に代表的なツールを紹介します。
【文章を作るAI】
-
ChatGPT(対話形式)
-
Gemini(Google製AI)
-
Claude(長文対応が得意)
-
Microsoft Copilot(WindowsやOfficeと連携)
-
Notion AI(メモや議事録作成に強い)
-
Perplexity AI(調べ物や解説に活用)
【画像を作るAI】
-
Midjourney(芸術的な画像)
-
Stable Diffusion(カスタマイズ可能)
-
DALL-E 3(ChatGPTと連携)
-
Adobe Firefly(商用利用対応)
-
Canva AI(デザイン編集と統合)
【コードを書くAI】
-
GitHub Copilot(プログラム補完)
-
Amazon CodeWhisperer(AWSと連携)
-
Tabnine(多言語対応、プライバシー重視)
-
Code Llama(Meta社のオープンソース)
-
Colab AI(Google Colab向け)
【音楽・音声を作るAI】
-
Suno AI(歌付き楽曲を生成)
-
Udio(高品質な音楽制作)
-
AIVA(映画風BGM)
-
Soundraw(ムード別BGM)
-
ElevenLabs(自然な音声合成)
【その他の便利なAI】
-
Runway、Pika(動画生成)
-
Gamma、Tome(プレゼン資料作成)
-
Elicit、Consensus(研究補助)
多くのサービスはスマホやタブレットにも対応しており、無料でも試せるものが多数あります。
3.自分に合ったAIを選ぶコツ
目的に合った生成AIを選ぶには、以下のポイントを参考にするとよいでしょう。
-
アカウント登録が必要かどうか
-
自分の目的に合っているか(例:文章、画像、音楽、コード)
-
日本語に対応しているか
-
操作が簡単で使いやすいか
-
無料プランがあるか、費用はどれくらいか
-
商用利用できるか
-
スマホやタブレットで使えるか
-
学割や学生向けプランがあるか

たとえば「授業で使いたい」「趣味でマンガを描きたい」など、自分の目標を明確にすると選びやすくなります。最初は無料で試せるサービスを使って、自分に合っているか確認してから有料版を検討するのがおすすめです。
4.日本でも広がってる!生成AIの活用例
日本国内でも、生成AIの導入が進んでいます。以下は実際の活用例です。
-
会社の会議資料や報告書の下書きをAIが作る(時間短縮、ミスの削減)
-
広告のキャッチコピーをAIが考える(効率的なアイデア出し)
-
SNS投稿用の画像や動画を自動生成(短時間で魅力的なコンテンツ作成)
-
プログラミング作業をAIが補助(エラー検出やコード提案)
-
教材作成にAIを使う(先生の負担軽減、個別対応可能)
-
企業サイトの文章作成をAIが支援(コスト削減、品質安定)

教育現場や広告、IT、建設、通信など多くの分野で導入されており、「ELYZA Pencil」「Catchy」など日本語に特化したAIも注目されています。
5.生成AIのこれからと注意すべきこと
今後、生成AIはさらに進化すると予測されています。
-
動画や3Dデータも簡単に生成可能になる
-
医療や教育など専門分野での活用が進む
-
アプリやソフトとの連携が拡大
-
著作権や倫理問題に対するルール整備が進行
-
自分の声で読み上げてくれるAIの登場

ただし、AIが出した内容は必ずしも正確ではありません。間違った情報が含まれることもあるため、使う前に確認する習慣が大切です。また、他人の作品と似すぎないようにする、出典を明記するなど、使い方のマナーやルールも意識しましょう。
おわりに
生成AIは、私たちの学びや創作活動をサポートしてくれる強力な道具です。難しそうに感じるかもしれませんが、使ってみると意外と簡単です。
勉強、趣味、将来の仕事に役立つかもしれないので、まずは自分に合ったツールを選んで試してみましょう。友達と一緒に使うことで、楽しみながらスキルを高めることもできます。
AIはあくまで「道具」です。あなたのアイデアや努力を引き出してくれる、未来の頼れる相棒になるでしょう。
今のうちからAIに触れておくことが、これからの可能性を大きく広げる第一歩になるはずです。

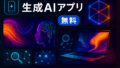
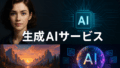
コメント