- はじめに
- 1 はじめに 過去問がないのは本当ですか?
- 2 試験の基本 まずここを押さえましょう
- 3 よく出るテーマと学び方のコツ
- 4 合格戦略の三本柱 過去問に頼らない学び方
- 5 アウトプット練習で定着を強くする
- 6 教材の選び方 目的別のおすすめ
- 7 誤答ノートの作り方とサンプル文
- 8 シラバスの地図 どこに時間を使う?
- 9 章別ミニ練習 その場で理解チェック
- 10 点を伸ばすコツ 第4章と第5章の攻略
- 11 プロンプトの型テンプレ すぐ使える3種
- 12 学習時間モデル 自分に合うパターンを選ぶ
- 13 1週間サンプル時間割 忙しくても回せます
- 14 当日のチェックリスト 直前の不安を減らす
- 15 トラブル対策 こうすれば落ち着けます
- 16 よくある質問 高校生目線のQ&A
- 17 ミニ用語辞典 まずはここから
- 18 まとめ 過去問に頼らず合格へ
- 付録A 学習管理テンプレート
- 付録B 10分仕上げチェック 直前に見るだけ
- 付録C すぐ使える練習課題 先生モードで説明してみよう
はじめに
このガイドでは、生成AIパスポート試験に向けて、公式の過去問がない状況でも効率的に学習し、合格点を獲得するための戦略を解説します。シラバスに基づいた学習方法、模擬試験の活用法、頻出テーマの攻略、そして効果的なアウトプット練習を通じて、最短距離で合格を目指しましょう。高校生でも理解しやすいように、具体的な例やテンプレートを交えながら、丁寧に解説します。
1 はじめに 過去問がないのは本当ですか?
生成AIパスポートでは、公式の過去問は公開されていません。これは、暗記だけで点を取る学習を避け、考える力と安全に使う力を確かめるための設計です。過去問探しに時間をかけるより、シラバスに沿った教材と模擬試験で実力を作ることが合格への近道です。本記事は、授業を数回受けた高校生でも迷わず進められる勉強計画を、具体例やテンプレート付きでやさしく解説します。
2 試験の基本 まずここを押さえましょう
試験形式は、60分間で60問の多肢選択式問題に解答する形式です。出題範囲は主に以下の4つの領域に分かれています。
-
AIの基礎知識
-
生成AIの仕組み
-
社会におけるルールと倫理
-
効果的なプロンプトの作成方法
時間配分としては、「1問あたり1分」を目安とし、解答に迷う問題は一旦保留(フラグを立てる)し、最後に再度検討するようにしましょう。
3 よく出るテーマと学び方のコツ
以下は、試験で頻出されるテーマと、それらを効果的に学習するためのコツです。
-
教師あり学習と教師なし学習の違い: これらの学習方法の違いを、具体的な例を挙げて自分の言葉で説明できるように練習しましょう。
-
生成AIの強みと弱み: 生成AIが得意なこと(例:文章の要約)と苦手なこと(例:事実の正確性保証)を、身近な例を用いて説明できるようにしましょう。
-
ハルシネーション: ハルシネーションの意味と、それを防ぐための対策(例:情報源の明示、指示の具体化)をセットで覚えましょう。
-
著作権・肖像権・個人情報保護: これらの権利に関する基本的な知識を、学校生活やSNSの利用場面に置き換えて考え、理解を深めましょう。
-
プロンプトの型: 様々なプロンプトの型を覚え、実際に生成AIに入力して、その効果の違いを体感しましょう。

4 合格戦略の三本柱 過去問に頼らない学び方
過去問がない状況でも、以下の3つの柱を意識することで、効果的に合格を目指せます。
-
公式テキストの精読: 公式テキストを丁寧に読み込み、太字、図、表などを活用して、全体像を把握しましょう。
-
反復学習と用語の理解: 毎日少しずつ反復学習を行い、重要な用語を自分の言葉で説明できるようになるまで練習しましょう。
-
模擬試験の活用: 模擬試験を活用して時間配分を練習し、間違えた問題については、その理由を必ず言語化して理解を深めましょう。
特に、シラバスの第4章(安全な利用)と第5章(プロンプト作成)は出題比重が高いため、学習時間を多めに配分しましょう。
5 アウトプット練習で定着を強くする
学習内容を定着させるためには、積極的にアウトプット練習を行いましょう。
-
用語カードの作成: 用語カードを作成し、表面に用語、裏面に簡潔な定義を記述します。
-
説明練習: 友人や家族に、学習した内容を30秒で説明する練習をします。
-
要点まとめ: 自分が先生になったつもりで、学習内容の要点を3行で板書するつもりでまとめます。
-
誤答ノートの作成: 誤答ノートを作成し、「なぜ間違えたのか」を1行で記述します。翌日、誤答ノートの問題だけを解き直し、同じミスを防ぎます。

6 教材の選び方 目的別のおすすめ
下の表は、よく使われるリソースを役割で整理したものです。重複を避け、効率よく学べます。
表1 教材の役割一覧
要点の箇条書き要約
7 誤答ノートの作り方とサンプル文
誤答理由は次の3分類で整理します。
知識不足:用語や定義を忘れていました。
読み違い:問題の条件を見落としました。
判断ミス:似た選択肢の違いを整理できていませんでした。
サンプル文:
誤答理由=読み違い。「条件『個人情報の匿名化』があるのに見落とした」。
次の対策=「条件に下線を引いてから選択肢を読む」。
同じテーマをタグ付けして、後でまとめて復習できるようにします。
8 シラバスの地図 どこに時間を使う?
シラバスは5章構成です。下の表は目安の配点バランスです。学習時間の配分に活用してください。
表2 章別の目安配点と学習ポイント
学習配分バー(時間配分の目安)
第4章と第5章で試験の半分以上を占めます。先に重点章を伸ばすと、点数のばらつきが少なくなります。仕上げの三手順として、①要点の音読、②設問の型を3題だけ解く、③誤答ノートの弱点タグを再チェック、の順で回すと安定します。
9 章別ミニ練習 その場で理解チェック
第1章:事例を見て「学習の種類」を言い当てます。
第2章:同じ指示を少し変えて、生成結果の違いを観察します。
第3章:ニュース記事を1本選び、どの章の知識に関係するかメモします。
第4章:シナリオを作り、何がOKで何がNGかを箇条書きにします。
第5章:自分の好きなテーマで要約指示を書き、改善を3回繰り返します。
10 点を伸ばすコツ 第4章と第5章の攻略
第4章は「安全に正しく使うためのルール」を問う章です。著作権や個人情報の扱いなど、具体的な場面で正しい選択をします。第5章は「伝わるプロンプト作り」がテーマです。
11 プロンプトの型テンプレ すぐ使える3種
・説明型:役割=説明者/条件=3行で、中学生にも分かる例を入れる/指示=「次の用語を説明して」。
・要約型:役割=編集者/条件=200字、箇条書き2点、重要語は太字/指示=「次の文章を要約して」。
・比較型:役割=先生/条件=表形式、似ている点3・相違点3/指示=「教師ありと教師なしの違いを比較して」。

12 学習時間モデル 自分に合うパターンを選ぶ
初学者(20〜30時間)
基礎:テキストを2〜3周して全体像と要点をつかみます。
強化:クイズアプリで用語を反復し、ノートに一言で要約します。
応用:問題集で選択肢のどこが違うかを、言葉で説明します。
模試:60分で解いて時間配分を体に覚えさせます。
既学習者(10時間前後)
最初に模試で弱点を見つけます。 第4章と第5章に時間を集中的にかけます。 最後に通読と模試を1回ずつ行い、穴をふさぎます。
13 1週間サンプル時間割 忙しくても回せます
月:テキスト第1章(30分)。用語カード5枚を作成します。
火:クイズアプリ(15分)+誤答ノート更新(15分)。
水:テキスト第4章(30分)。ルールを生活例に置き換えます。
木:問題集(30分)。誤答の理由を1行で書きます。
金:プロンプト練習(30分)。型テンプレを使います。
土:模試(60分)+復習(30分)。
日:休息。15分だけ弱点カードを見ます。
14 当日のチェックリスト 直前の不安を減らす
PC・ブラウザ・カメラ・マイクの動作確認をします。 身の回りを片づけ、禁止事項を読み直します。 第4章・第5章の要点メモを最終確認します。 早めに寝て体調を整えます。 試験中は、分からない問題に印を付けて後で戻ります。 終了3分前に全問チェックを行います。
15 トラブル対策 こうすれば落ち着けます
回線が不安定なときは、ルーター再起動→有線接続→可能なら別回線の順に試します。 画面が固まったら、焦らず再読み込みをします。再入室の可否は事前に確認します。 周囲の雑音が気になる場合は、静かな部屋を確保し、家族に時間を共有します。
16 よくある質問 高校生目線のQ&A
Q. 過去問がないと不安です。
A. 大丈夫です。シラバス準拠の教材と模試で十分に練習できます。
Q. 公式クイズアプリだけでいけますか。
A. 用語確認には最適ですが、本番形式は問題集や模試で練習します。
Q. どこから勉強を始めればよいですか。
A. まず通読して全体像をつかみ、早めに第4章と第5章に取りかかります。
Q. 1日どれくらい勉強すればいいですか。
A. 平日30分・週末90分を基本に回します。無理のないペースが長続きします。
Q. 模試で点が伸びません。
A. 誤答ノートの3分類で原因を特定し、同じタイプの問題を集中的に解き直します。
17 ミニ用語辞典 まずはここから
ハルシネーション:AIが「もっともらしい誤情報」を出すことです。 プロンプト:AIへの「指示文」のことです。
教師あり学習:正解付きデータで学ぶ方法です。
教師なし学習:正解なしデータの「パターン」を学ぶ方法です。
個人情報保護:個人を特定できる情報を守る考え方です。
18 まとめ 過去問に頼らず合格へ
過去問は公開されていませんが、心配はいりません。テキストで土台を作り、毎日の反復と模試で力を付けましょう。特に第4章と第5章を強化すれば、初見の問題でも落ち着いて対応できます。自分に合ったペースで、合格へ一歩ずつ進みましょう。合言葉は「昨日の自分より1歩前へ」です。
付録A 学習管理テンプレート
学習計画や誤答の記録に使えるスプレッドシートを用意しています。下のリンクから複製して使ってください。
学習テンプレートを開く
付録B 10分仕上げチェック 直前に見るだけ
AIの基礎の定義を1行で言えます。 生成AIの強みと弱みを1つずつ言えます。
ハルシネーションの意味と対策を1つ言えます。
著作権と個人情報の注意点を1つずつ言えます。
良いプロンプトの型(役割・条件・例)を思い出せます。
付録C すぐ使える練習課題 先生モードで説明してみよう
自分の好きな科目をテーマに、要約用プロンプトを作ります。
友だちに30秒で「ハルシネーション」を説明します。
最近のニュースを1つ選び、AIに関係する点を2つ挙げます。
身の回りの写真や作品の利用で、著作権や個人情報に気をつける例を考えます。

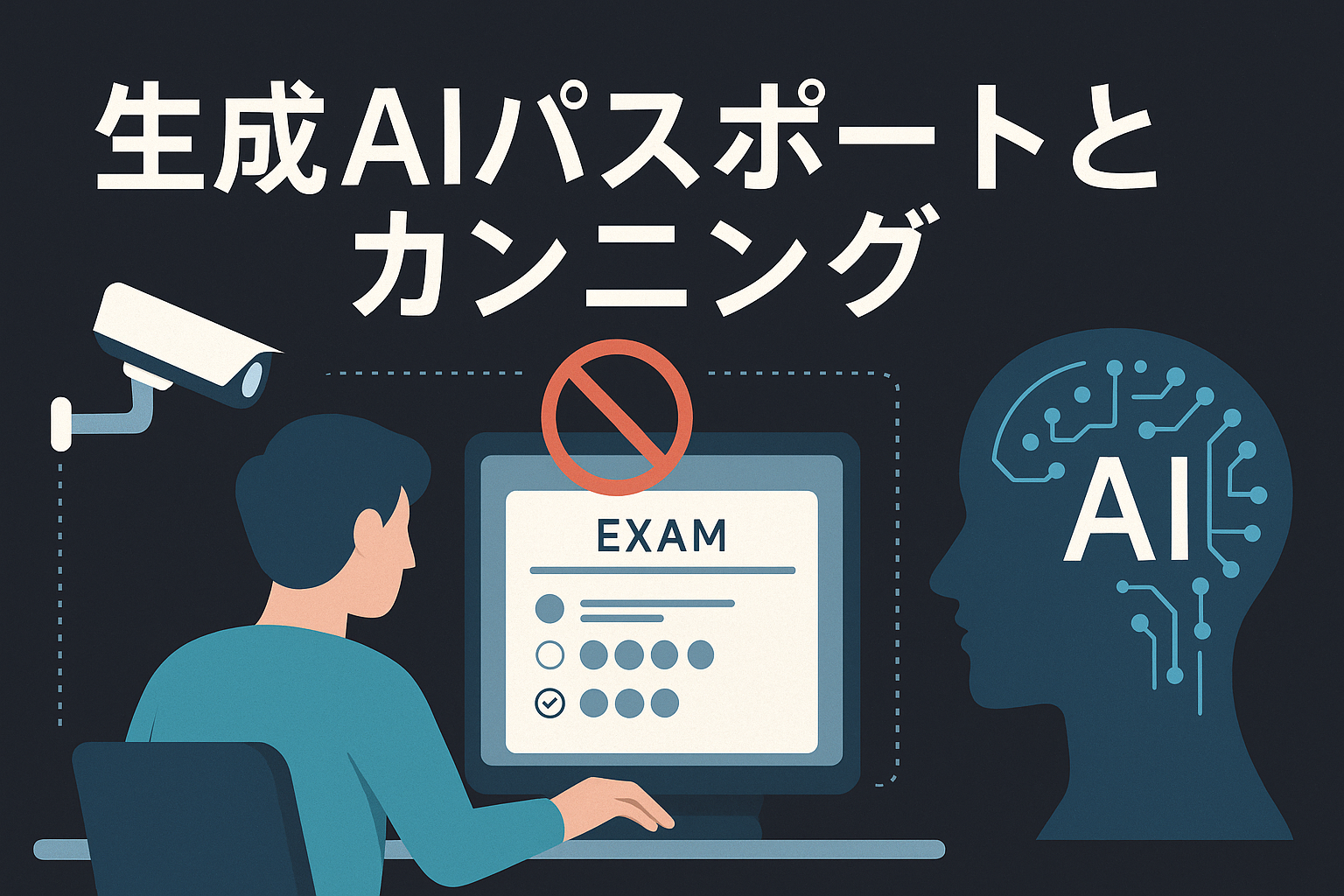
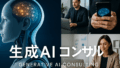
コメント