はじめに
このドキュメントは、高校生向けに「生成AIパスポート」資格試験に関する公式情報をわかりやすくまとめたものです。公式サイトや関係省庁の情報を参照し、試験の概要、合格率、運営団体、政府のガイドライン、他の資格との比較、教育分野での活用について解説します。-visual-selection.png)
(最終確認日:2025年9月1日)
I. 試験の基本情報
生成AIパスポートは「AIを安全に使うための基礎力を証明する」ことを目的とした資格です。難しい計算やプログラミングではなく、AIを正しく理解し、リスクを回避する知識を身につけることに重きが置かれています。-visual-selection-1.png)
-
試験概要・申し込み:https://guga.or.jp/generativeaiexam/
(全国どこからでもオンラインで受験可能) -
学習の進め方:https://guga.or.jp/learning/
(1日1時間学習すれば数週間で受験可能) -
シラバス(出題範囲):https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf
(2024年改訂で「AI事業者ガイドライン」が反映) -
公式テキスト(第3版):https://guga.or.jp/qualification-exams/textbook/
-
Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/491091204X
II. 合格率と受験者数
この試験は「広く普及させる」ことを目的にしているため、合格率は70%後半と安定して高めです。努力すれば多くの人が合格できる設計になっています。-visual-selection-2.png)
-
2023年10月:https://guga.or.jp/2023-11-13/
-
2024年6月(要約記事):https://di-manager.com/ai-news/20240719/
-
2024年10月:https://guga.or.jp/2024-11-18/1300
-
プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000121559.html
※2025年6月時点で、資格取得者は累計2万人を突破しています。
III. 運営団体:GUGA
試験を運営するのは「一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)」です。「普及」という言葉が示す通り、AIを専門家だけでなく社会全体に広めることを使命としています。-visual-selection-3.png)
-
公式サイト:https://guga.or.jp/
-
設立ニュース(2023/05/10設立): https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000121559.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000121559.html -
デジタル証明(オープンバッジ): https://openbadgepassport.com/app/issuer/badges/27420?hl=ja
-
生成AI人材認定カード:https://guga.or.jp/recognitions/
-
取材記事:https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2307/20/news097.html
※オープンバッジはSNSや履歴書に載せられるデジタル証明で、就職活動にも活用できます。
IV. 政府の関連ガイドライン
生成AIパスポートの出題には、政府が発表したルールが反映されています。これにより、AIを安全に使う方法や、情報漏えいを防ぐ知識を学ぶことができます。-visual-selection-4.png)
-
総務省「AI事業者ガイドライン」:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban10_02000411.html
-
経産省「AI事業者ガイドライン」:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ai/ai_rule.html
V. 他の資格との比較
生成AIパスポートの特徴を理解するには、他の資格との比較が役立ちます。-visual-selection-5.png)
G検定(JDLA)
-
合格率データ:https://www.jdla.org/news/2024-01-31-01
(AIの歴史や理論も含まれるため、やや難易度は高め)
ITパスポート(IPA)
-
合格率データ:https://www.itpass.jp/ex30/statistics/statistics.html
(国家資格で、IT全般の基礎知識が問われる)
→ まとめ:
-
ITパスポート:IT全体の基礎を広く学ぶ入門資格。
-
生成AIパスポート:生成AIに特化し、安全な実務活用を重視。
-
G検定:より専門的で高度なAI知識を扱う資格。
-visual-selection-6.png)
VI. 教育分野での活用
生成AIパスポートは企業研修だけでなく、教育の場にも広がっています。例えばTOSS(先生の研究団体)と連携し、学校でのAI活用や校務効率化に役立てられています。-visual-selection-8.png)
VII. ポイントまとめ
-
出題範囲や対象者は公式ページが最も信頼できます。
-
シラバスには最新のガイドラインが反映されています。
-
合格率は安定して高く、学習すれば合格しやすい資格です。
-
比較対象は「G検定」「ITパスポート」。位置づけを理解すれば進むべき資格の道が見えます。
-
企業だけでなく学校教育でも使われており、今後さらに広がる可能性があります。
-visual-selection-9.png)

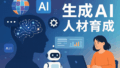
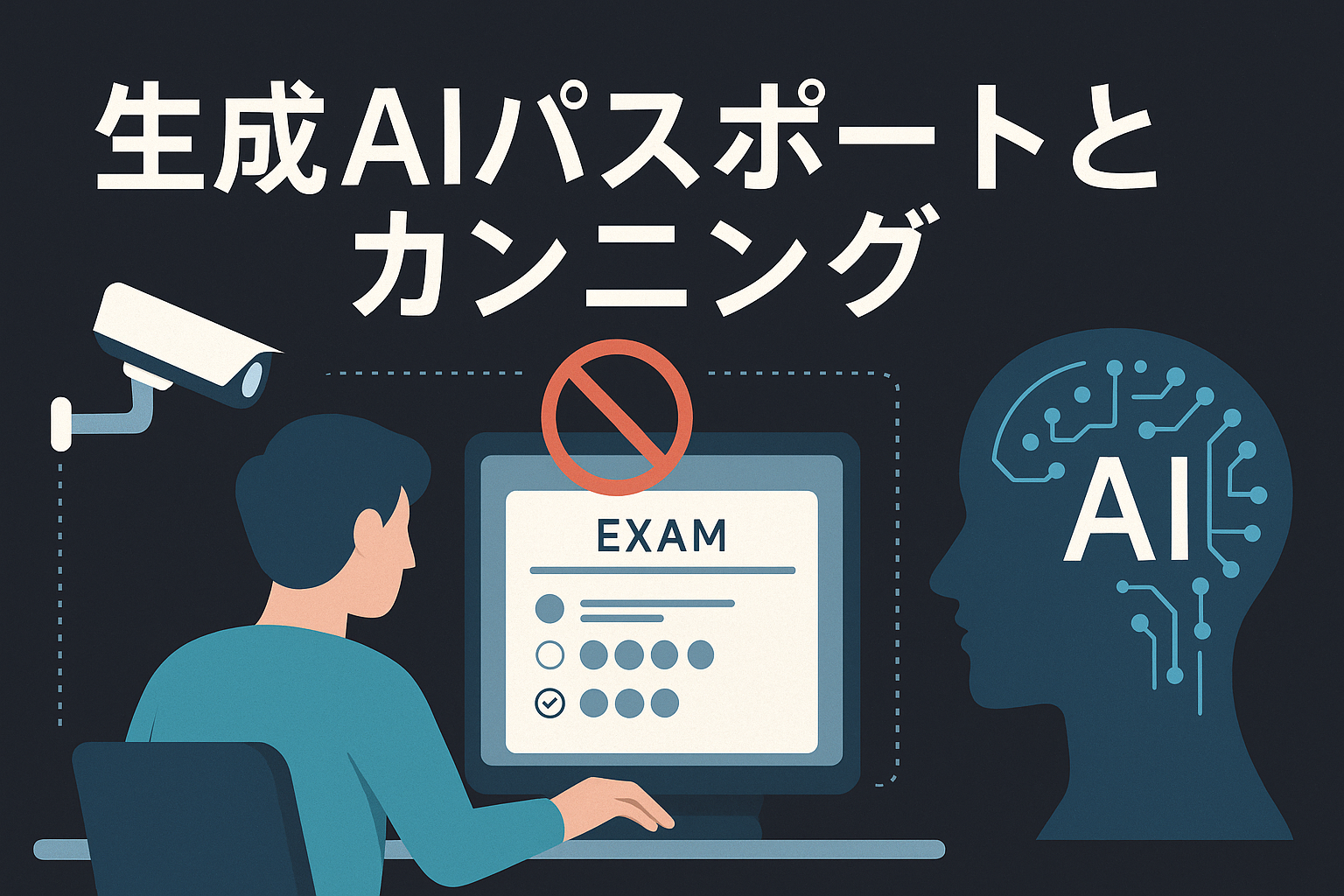
コメント