【はじめに】
最近、テレビやSNS、そして授業でも「生成AI(ジェネレーティブAI)」という言葉を聞く機会が増えました。これは、AIが文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったり、プログラムを組んだりすることができる新しい技術です。
このAIを動かすために必要なのが「プロンプト」と呼ばれる“お願い”や“指示”です。うまく伝えれば、AIはとても便利で役立つ答えを返してくれます。
この記事では、「プロンプトって何?」「どう書けばうまくいくの?」といった疑問にわかりやすく答えていきます。さらに、上手な使い方、注意点、そして将来の展望についても紹介します。
1. プロンプトって何?
プロンプトとは、AIに「こんなことをしてね」とお願いする文章のことです。
たとえば、
・「この文章をやさしい言葉に書き直して」
・「かわいい柴犬のイラストを作って」 といったものも、すべてプロンプトです。
プロンプトに含まれる主な要素は次の4つです。
・何をしてほしいか(指示)
・どんな背景や目的があるか(文脈)
・どのような材料を渡すか(入力データ)
・どんな形で返してほしいか(出力形式)
たとえば、「この英文を中学生向けに、わかりやすい日本語で説明してください」といった形で、目的・対象・内容を具体的に書くと、AIも意図を理解しやすくなります。
2. 上手なプロンプトの作り方
AIに正確に動いてもらうには、伝え方に工夫が必要です。次のようなポイントを押さえましょう。
・あいまいな表現(「いい感じに」など)を避けて、具体的に書く
・やってほしいことを明確に伝える
・情報が多いときは、箇条書きや段落で整理する
・「〜してください」といった丁寧で前向きな表現を使う
・一度で完璧を目指さず、少しずつ改善していく
画像を作るAIには、「これは入れないで」と伝える“ネガティブプロンプト”も役立ちます。 (例:「手が6本にならないようにしてください」など)
AIを使いながら、「こうすればもっと良くなるかな?」と試行錯誤することで、プロンプトの書き方も上達していきます。
3. プロンプトエンジニアリングって何?
プロンプトエンジニアリングとは、AIがよりよく動けるように、プロンプトを工夫して設計する技術のことです。
基本的な方法には次のようなものがあります。
・ゼロショット:例を見せずに直接お願いする
・フューショット:いくつかの例を見せてからお願いする
・役割設定:AIに「あなたはプロの編集者です」などと役割を与える
さらに、応用的な方法もあります。
・思考の連鎖(Chain of Thought):答えを出す前に、考え方の過程を説明させる
・ReAct:AIに考えさせながら、必要な行動(検索など)をさせる
・RAG:AIが自分で外部情報を探してから答える
・自己整合性:いくつかの回答を出させて、一番よいものを選ぶ
こうした工夫を加えることで、AIの答えの質をさらに高めることができます。
4. 文章・画像・コードでの使い分け
プロンプトの書き方は、目的によって少しずつ異なります。
【文章生成】
・文章のトーン(ていねい、カジュアルなど)
・対象読者(小学生向け、大人向けなど)
・形式(箇条書き、段落、要約など)
【画像生成】
・主な被写体(人、動物、建物など)
・雰囲気(明るい、幻想的、暗めなど)
・スタイル(アニメ調、写実的、水彩画風など)
【コード生成】
・使いたいプログラミング言語(Python、JavaScriptなど)
・どんな動きをしてほしいか(関数、ツールなど)
・条件(例:エラー処理を入れてください など)
それぞれの分野で、AIが理解しやすいように、的確な情報を伝えることが大切です。
5. 活用されている場面
生成AIは、すでに多くの場面で使われています。
・ブログ記事やSNS投稿の作成
・マーケティングでのキャッチコピーや広告文の作成
・学校の課題や参考資料の補助 ・アプリやサービス開発の支援
・小説、マンガ、脚本などのストーリー構成
・音楽やビジュアルアートの創作
・病院での記録整理や診断の支援
・情報セキュリティの分析や対策
最近では、高校の授業でもAIを活用する試みが始まっています。難しいテーマをかみくだいたり、アイデアを広げたりするのに便利です。
6. 注意すべきこととリスク
とても便利なAIですが、使い方によっては思わぬトラブルを招くこともあります。
・あいまいなプロンプトでは、意図と違う回答になることがある
・AIが事実でない情報(ハルシネーション)を出すことがある
・悪意のある指示で不適切な答えを出してしまうことがある
・偏見や差別につながる表現が出ることがある
だからこそ、AIの出力はうのみにせず、自分でもしっかり確認・判断することが大切です。
7. 安全で正しい使い方を考えよう
AIは便利な道具ですが、正しく使う責任は人間にあります。
・個人情報を不用意に入力しない
・他人の著作物をそのまま使わない(著作権に注意)
・不快な表現や攻撃的な内容を避ける
・AIの答えを「なぜこうなったのか」と考える習慣を持つ
プロンプトを書くときは、「この使い方は正しいかな?」と立ち止まって考えることが、とても重要です。
8. これからの進化と未来の可能性
これからのAIとプロンプトの世界は、ますます進化していくと考えられます。
・AIが自動で最適なプロンプトを考えてくれるようになる
・文字だけでなく、画像や音声も組み合わせた指示が使えるようになる
・一人ひとりに合わせた“パーソナライズされた指示”が可能になる
・プロンプトを書くこと自体が仕事になっていく
つまり、「プロンプトを書く力」は、未来の仕事や生活にもつながる、大切なスキルになるかもしれません。
【おわりに】
生成AIは、とてもおもしろくて、役に立つ道具です。 でも、「どう使うか」を自分で考えることが、もっと大切です。
プロンプトは、AIと人間が協力して何かをつくるためのスタートラインです。工夫すればするほど、AIはあなたの力になってくれます。
この文章を読んで、プロンプトづくりに挑戦してみようと思ってくれたならうれしいです。 勉強や創作、将来の仕事にもつながるかもしれません。
ぜひ、自分のアイデアをAIと一緒にカタチにしていきましょう!

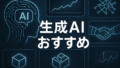
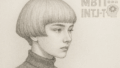
コメント