↑ChatGPT Soraで生成AI動画!猫からカラスに変身!ゴミ捨て場でバレーボール⁈
【はじめに】
本ドキュメントでは、近年注目を集めている「生成AI」について、高校生にも理解できるように解説します。生成AIは、AIが自動で文章や画像、音楽、動画などを生成する技術であり、その基本的な概念から具体的なアプリの種類、活用シーン、注意点、将来の可能性までを網羅しています。これを通じて、生成AIの魅力とその利用方法を学び、実生活に役立てることができるでしょう。

近年話題の「生成AI」は、AIが自動で文章や画像、音楽、動画などをつくり出すすごい技術です。このガイドでは、生成AIアプリの基本から使い道、注意点、将来の可能性までを、高校生にもわかるやさしい言葉で解説していきます。
1.生成AIアプリってなに?
生成AIアプリとは、AI(人工知能)がゼロから新しいコンテンツを生み出すアプリです。たとえば文章、イラスト、音楽、プログラム、音声、動画などを、自動でつくってくれます。
今までのAIは、決まったルールやパターンに従って判断や予測をするのが得意でした。たとえば、猫の画像を見分けたり、天気を予想したりするなどです。でも、生成AIは「つくること」が得意です。アイデアを形にしてくれる、とてもクリエイティブなAIなのです。
たとえば「明日の朝ごはんを考えて」とAIにお願いすると、ちゃんと提案を返してくれます。まるで未来のアシスタントのようで、使っていてワクワクする技術です。

2.生成AIアプリにはどんな種類があるの?
生成AIアプリにはさまざまな種類があり、それぞれに得意分野があります。
・テキスト生成アプリ(例:ChatGPT)… 文章の作成、要約、翻訳、メール文の提案など。
・画像生成アプリ(例:Midjourney)… テキストをもとにオリジナルの絵やイラストを作成。
・コード生成アプリ(例:GitHub Copilot)… プログラムコードを自動で作ったり、間違いを直してくれたりします。
・音声・音楽生成アプリ… 曲やBGM、ナレーションなどを自動で作ってくれます。
・動画生成アプリ(例:Sora)… テキストからアニメーションや短い動画を作ってくれます。

これらのアプリは、「Transformer(トランスフォーマー)」や「拡散モデル」などの先進的な技術を使って動いています。細かいしくみは難しいかもしれませんが、「AIの脳みそがどんどん賢くなってきている」と思ってもらえればOKです!
3.よく使われている人気の生成AIアプリ
ここでは、特に注目されている代表的な生成AIアプリを紹介します。

ChatGPT(OpenAI) テキスト生成AIの代表格。質問に答えたり、文章を書いたり、詩を作ったり、簡単なコードも生成可能。日本語にも対応しており、学習や調べものにも便利です。
Midjourney アートやイラストに特化した画像生成AI。プロンプト(指示)を入力するだけで、美しいビジュアルを自動で作ってくれます。芸術表現におすすめです。
Canva もともとはプレゼン資料やSNS画像などをデザインするツール。今ではAIによる画像生成や文章の要約、デザイン提案などが可能に。誰でもプロっぽい作品を作れるのが魅力です。
GitHub Copilot プログラミング支援に特化したAI。入力中のコードを予測して補完したり、関数全体を生成したりできます。英語がベースですが、理系の学生にも人気があります。
Sora(OpenAI) OpenAIが開発中の動画生成AI。テキストの説明から短い動画を生成でき、将来的に大きな注目を集めると予想されています(2024年ごろ一般提供予定)。
4.どこで使われている?
生成AIの活用シーン 生成AIはすでに多くの分野で活用されています。具体的には、以下のような場面があります。
・ビジネス:広告文やホームページの文章作成、商品説明などに利用。
・教育:教材作成、問題文や解説文の生成、授業準備の効率化。
・研究:文献の要約やデータ分析、グラフ生成、仮説作成の支援。
・クリエイティブ:イラストや音楽、動画、マンガの構想、プロット作成など。
・日常生活:LINEの返信文、SNSの投稿文、プレゼントのメッセージ文などの作成。

たとえば「母の日のメッセージを考えて」と入力すると、あたたかい言葉で文章を提案してくれます。気持ちを伝えるのが少し苦手な人にも心強いツールです。
5.使うときに気をつけるポイント
生成AIはとても便利な一方で、注意すべき点もあります。以下のことに気をつけながら使いましょう。
・間違った情報を正しく見せてくることがあります(「ハルシネーション」と呼ばれます)。
・既存の作品と似た内容になる可能性があり、著作権に注意が必要です。
・個人情報(住所、電話番号など)を入力すると、情報漏洩のリスクがあります。
・生成された内容に失礼な表現や不適切な文章が含まれる場合があります。

大切なのは、「そのまま使う」のではなく、「内容をチェックして、自分の言葉として使う」ことです。AIを頼りにしすぎず、自分で考える力も一緒に育てていきましょう。
6.これからの生成AIの未来
生成AIの技術はこれからさらに進化していくと考えられています。以下のようなトレンドが注目されています。
・マルチモーダルAI:テキスト、画像、音声、動画などを一つのAIで扱えるようになる。
・パーソナライズ:一人ひとりの好みやニーズに合わせた内容を提供するAIの進化。
・オンデバイスAI:クラウドではなくスマホやパソコン上で動く軽量AIの登場。
・AIエージェント:AIが自律的に考え、複数のタスクを計画的に実行するようになる。

ただし、技術が進むことで「人の仕事が減る」「AIが悪用される」などの課題も出てきます。だからこそ、便利さとリスクの両方を理解した上で、社会全体でルールを考えていくことが大切です。
【まとめ】
生成AIは、文章・絵・音楽・動画などを自動で作ってくれる、これからの時代を支える重要な技術です。まずは無料のアプリを試してみて、どんなことができるのか、自分で体験してみるのがおすすめです。
そして使うときは、「AIにまかせっぱなし」ではなく、「自分で内容を確認して使う」ことを忘れないようにしましょう。生成AIとうまく付き合う力は、これからの学びや仕事、生活の中できっと役立ちます。


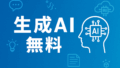
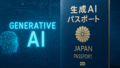
コメント